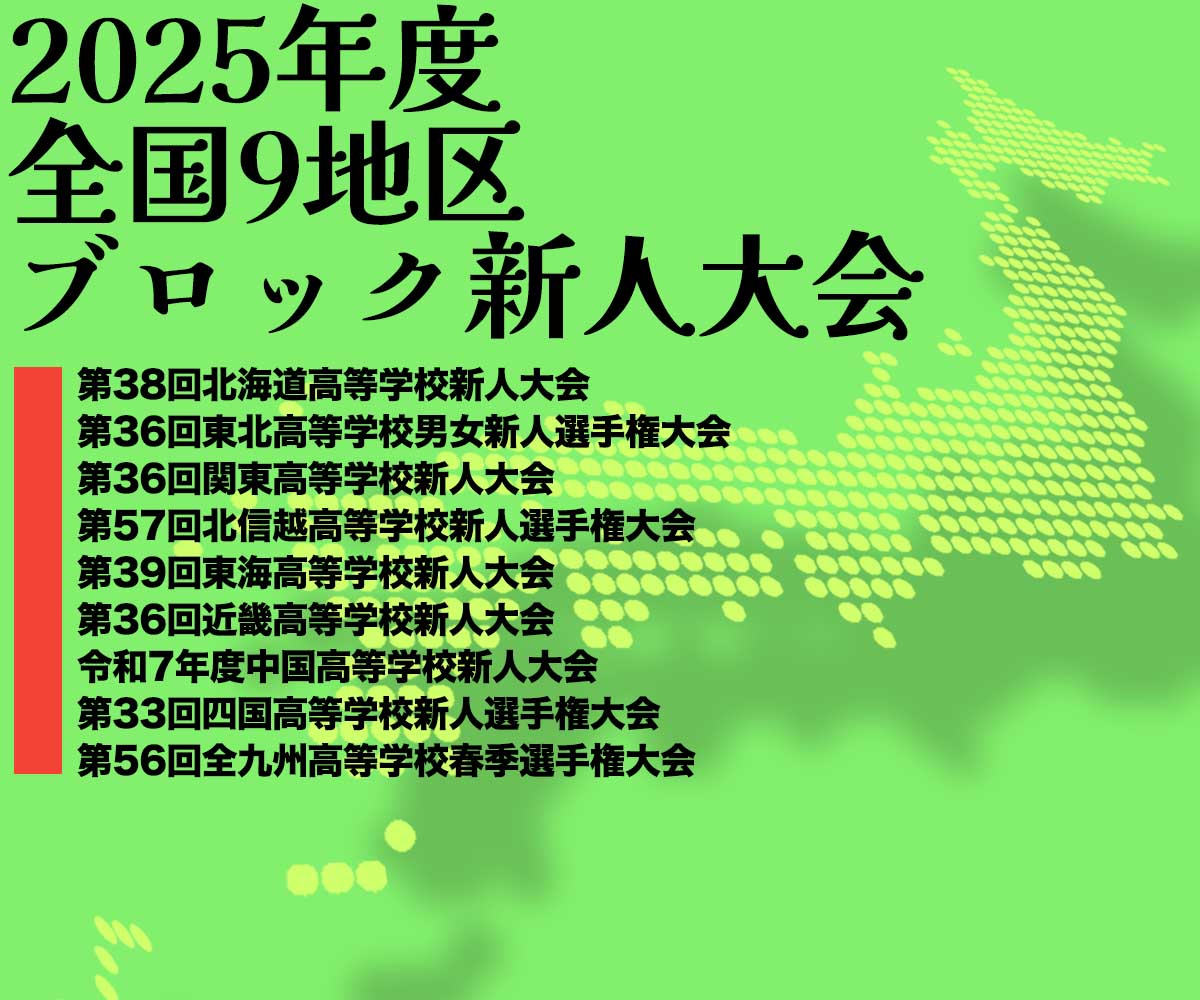【女子アジアカップ現地レポート】個々の力がチーム力として結実し、“深いバスケット”で果たした4連覇!
試合終了のブザーが鳴り響き、選手たちが喜びを分かち合うようにコート中央で抱き合った。最終スコアは日本71-68中国。インドのバンガロールで開催された「FIBA女子アジアカップ」に、大会最多に並ぶ4連覇(4年連続5度目の優勝)という新たな歴史が刻まれた瞬間である。

決して楽に優勝できたわけではない。
「周りの国の人々も、『この大会はオーストラリアか中国が優勝する』と言っている。なぜ3回連続優勝しているうち(日本)の名前を言わないのかと、ちょっと熱くなるね」
大会中にトム・ホーバスHCがそう冗談めかして話していたように、日本は“絶対的な優勝候補”とは目されていなかった。事実、大会前の練習試合では中国に敗れており、今大会でも準決勝のオーストラリア戦(76−64)、決勝の中国戦と、ともに先にリードを奪われる我慢の展開。特に決勝戦は、2Q残り5分で一時10点差を開かれ、3Qに逆転したが一進一退が続いて4Q残り22秒で3点差に詰め寄られるなど、最後の一瞬まで全く気の抜けない試合だった。日本、中国、オーストラリアの上位3か国に、大きな力の差はなかったと言えるだろう。
ただ、それでも日本は苦しい試合を勝ち切った。負けることの許されない4連覇の重圧や、“打倒・日本”に燃える強敵たちの気迫をはね返し、文句なしに最強を証明したのだ。明暗を分けたもの、勝利をたぐり寄せた日本の強さとは、一体どこにあるのか。
日本語を流暢に話すホーバスHCが、準決勝後、決勝後と、くり返し口にしていた言葉がある。
「うちの深いバスケットをしたい」
「(日本は)気持ちが深い」
すなわち、“深い”というキーワードだ。
深いバスケット――そこにはさまざまな意味合いが含まれるだろうが、日本の戦いぶりを見ていておのずと連想されたのは、『徹底』の二文字だ。深い底まで貫き通すこと。それを日本は今大会を通じて、しつこくやり抜いた。
例えばキャプテンの#8高田は、準決勝でも決勝でも、苦しいときに仲間へこう声をかけていた。
「相手が疲れている今こそ、走ろう」
両チームが心身で疲弊する時間帯こそ、“走るバスケット”という日本の真骨頂を発揮する時。それをチーム全員で、再三確認し合っていたのである。
また、走力を生かすための生命線となったのが、ディフェンスとリバウンド。この2点に関して、特に泥臭く献身的な働きを見せたのが#10渡嘉敷だった。
「オフェンスではリズムをつかめなかったので、ディフェンスからしっかりリズムをつかもうと思って頑張りました。ディフェンスで崩れたら自分がいる意味がなくなってしまうので、何かしら一つ存在感を表すことができればと思っていました」
そう語る渡嘉敷は、見ていて感嘆するほどに、相手のビッグマンに対して激しくコンタクトし続け、簡単にはリング下でボールをもらわせなかった。リバウンドでもボックスアウトを徹底し、こぼれ球を#52宮澤や#88赤穂らが飛び込んで奪取。どちらかといえばこれまでオフェンスの印象が強かった日本の大エースが、数字以上のハードワークで、献身的に日本を支えていたのだ。
一方、オフェンスに目を転じれば、見る者を大いに魅了したのが#15本橋だ。「積極的に攻めることがチームに貢献できる私の仕事だと思ったので、勢いを付けるためにも、どんどん攻めて行こうと思っていました。迷いはなかったです」と、165cmの小柄な体でリングにアタック。スピードのミスマッチを突いて大きな相手を手玉に取り、特に準決勝では22点、決勝では24点とチームハイの得点を挙げてチームをけん引した。
この本橋や、決勝で3連続の3Pシュートを決めた#27林ら、今大会はベンチメンバーの活躍も勝敗の大きなポイントだった。スタメン、ベンチ関係なく、一人一人が自らにできることをチームのために徹底したからこそ、互角の戦いの中で勝利の女神が微笑んだのだろう。攻防にわたって個々の力がチーム力として結実し、日本の“深いバスケット”につながったのだ。
こうして、アジアカップは4連覇という最高の形で幕を閉じた。ただ、ホーバスHCは「この優勝はオリンピックのためにも、本当に大事で必要でした。日本の目標はそこ(オリンピックでの金メダル)にある」と、すでに次の戦いを見据えている。高田も「今のバスケットをもっともっと極めれば、世界の強豪とも戦える自信があります」と胸を張ってコメント。今大会の経験を糧にして、日本らしさを磨いた先に、悲願の表彰台があるはずだ。

※アジアカップの詳しい特集は、10月25日発売の月刊バスケットボール12月号で!
(月刊バスケットボール)