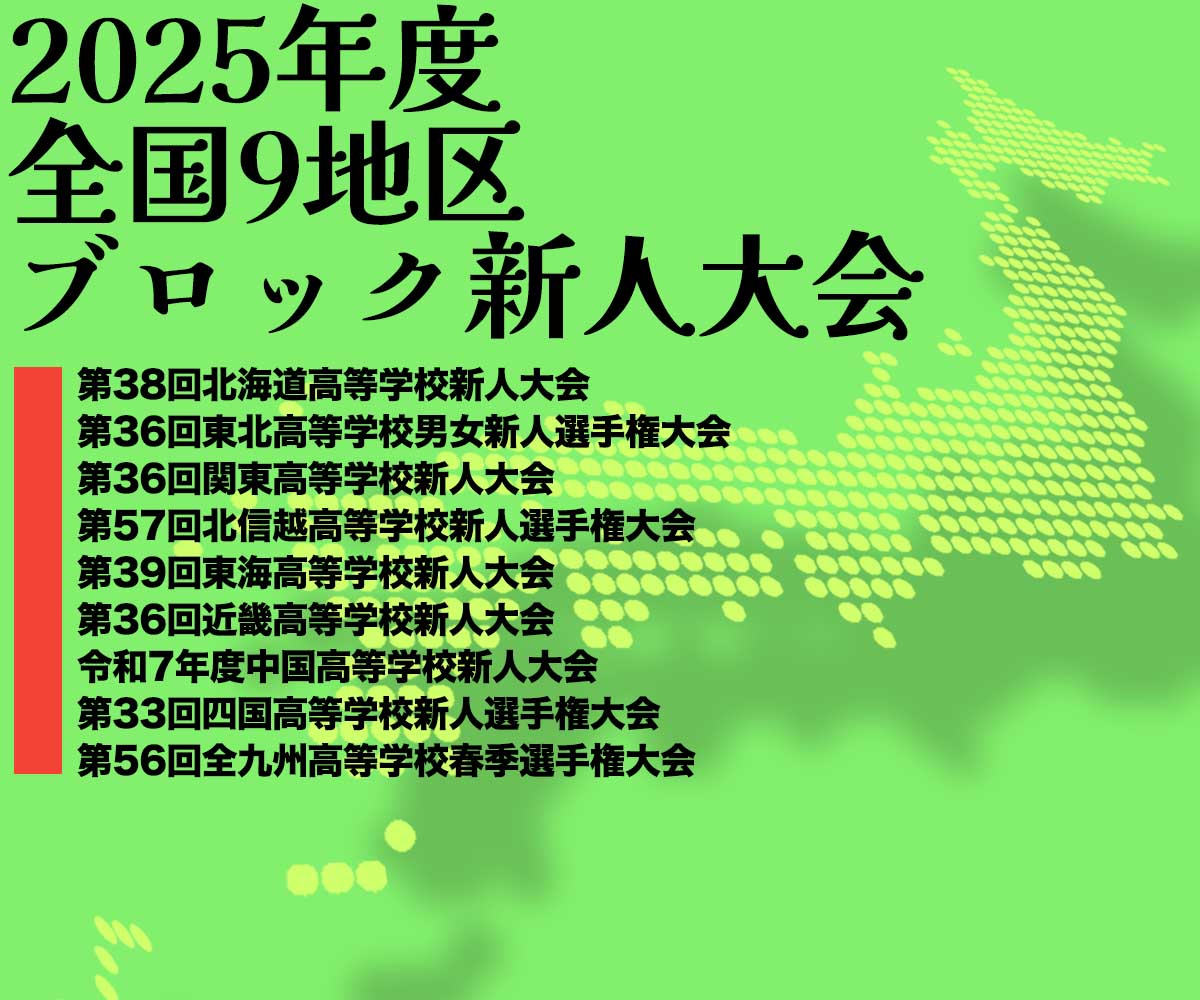北卓也GMと佐藤賢次HC、タッグ結成22季目の名コンビがお互いの関係性を語る

指導者として大切にしていること
──北GMは、現在はコーチ業から離れていますが、お二人が指導者として大切にしていることは何でしょうか?北 チームスポーツなので自己犠牲ですね。影になる選手がいるからこそ、ほかの選手が輝くわけですよね。だからこそ、そういう影の選手がスクリーンかけてくれたり、見えないところで貢献してくれていることに感謝しなければいけないと思います。『シュートを決めた俺がすごい』ではないんですよね。そういうバランスやチームの関係性が勝つためには絶対に必要です。ウチには長年ニック(ファジーカス)という柱がいて、それを支える周りの選手たちがいます。そこを忘れてはいけないです。
あとは、反応すること。コミュニケーションというのは何か言葉を言っても聞こえないければ成り立たないですよね。だから、仲間の声が聞こえたら何かしら反応しようとは話していましたね。
佐藤 今の北さんの話から思い出すこともあって、北さんはキーワードをよく僕らに話してくれていたんですよね。その中に「最善を尽くす」という言葉がありました。「最善を尽くす」と「ベストを尽くす」は意味が全く違います。後者は自分のベストを尽くすことであり、前者はその状況下で最も良い判断をすることです。「最善」の中には自己犠牲やコミュニケーション、臨機応変さなども含まれています。
北 バスケは状況が常に移り変わるスポーツなので、最終的には選手が判断しなければなりません。でも、そこで「コーチの言うとおりにやりました」と言われると、「ちょっと違うよね」となります。自分で判断してほしいですし、その判断の引き出しを与えるのがコーチの役割です。準備をして試合に臨むのは当然ですが、相手チームも準備してくるわけです。そこで自分たちの準備してきたことがうまくいかなかったとして、コーチが指示するまでそれを続けてしまうのではいけません。「相手がこうしてきたから、こう判断しました」というのは受け入れますね。
佐藤 そうなんですよ。自分で判断することが選手にとっては一番楽しいことですから。
北 それに、そこには絶対に責任が生まれてきますから、判断するためには努力しなければいけない。東芝には伝統的な部分もありましたが、僕自身はコーチになってからはスポーツ界のいろいろな方や企業のトップの方の言葉などを気にするようになったんです。何か良い言葉はないか、と。「最善を尽くす」という言葉も当時の東芝の社長が言っていたことで、それにすごく納得してチームでも話したんですよね。
佐藤 僕はヘッドコーチになるにあたって、伝統を引き継ぐことと、新しく取り入れることの両方を考えていました。ちょうどその時期はワールドカップをはじめ、日本が世界と対戦することが多いタイミングでした。そういう試合を見ていて、相手に先に準備をされたらこちらのやりたいことはできないと思っていたんですよね。例えばトランジションの場面では思考を早くして先に準備して、仕向けていかないと全てが後手になっていく。だから、新しく取り入れる部分として、僕が一番やりたかったのは先手を取ることでした。これまで築き上げてきたベースに加えて、メンタル的な計画立ての早さを加えてきました。
佐藤 そうですね。自分たちから仕掛けられるようなチームを目指して、やっている最中です。
──川崎はBリーグ開幕以降、エンターテインメントの部分で最も進化したクラブの一つです。お二人にとっては何が最大の変化でしたか?
北 Bリーグになったこと自体がすごく大きかったですね。僕らが選手だった頃は企業スポーツでしたから、東芝という企業のためにどれだけ存在価値を示せるのかと考えてやっていました。それが、Bリーグになってからは、川崎の皆さんのためにと、その規模がより大きくなったと思います。今は満員のアリーナで試合をするのが当たり前になってきました。ただ、それは決して“当たり前”ではないんです。昔は1000人観客が入ったら「今日はたくさん観客がいるね」と話していたし、逆に「今日は何で1000人もいるんだ?」というくらいでしたから(笑)。
佐藤 そうでしたよね(笑)。
北 本当にバスケットボールというスポーツが少しずつ皆さんの“日常”になってきているなと思いますし、やはりそれが一番の変化ですね。
佐藤 Bリーグの誕生は本当に大きな変化で、その中でさらにクラブのオーナーが東芝からDeNAに変わったことも大きいです。DeNAという企業が目指す理念はもちろん、我々、川崎ブレイブサンダースに課されたミッションが変化したときに、そこに向かっていけたというのは個人的に大きかったです。「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL 〜川崎からバスケの未来を〜」というミッションに共感しましたし、自分もその力になりたいと思いました。それと同じくして、ファミリーの皆さんも増えましたし、川崎というクラブの認知度も高まりました。いろいろな変化の中でみんなが力を合わせて、少しずつ大きくなったからこそ、今のクラブがあります。
認知度という面では、街で声をかけられる機会も少し増えて、それこそ、ラゾーナ川崎プラザに行くと声をかけられます。この前、息子とゲームセンターでシュートを打つゲームをしていたら、いつの間にかミニバスをしている子たちが僕の後ろにブワーッといたこともあったんです。「川崎のコーチだ!」って(笑)。でも、本当にありがたいことですよね。川崎には僕らやサッカーの川崎フロンターレをはじめ、たくさんのスポーツチームがあります。僕らも一つの川崎の顔として、もっといろんなことを還元していけたらなと思います。
佐藤 今季はコーチ陣のキャラがすごく濃いです(笑)。でも、みんなチーム思いでバスケが大好きだし、ハードワークしてくれます。そういうコーチの色が選手にも浸透してるような気がしていて、すごく助かっていますね。一つ面白い話があって、今季のある試合中に僕らのベンチの目の前で相手選手がちょっとだけラインを踏んだんですよ。そうしたらコーチ陣がみんな「今、ライン踏んだ!」と言わんばかりに同じ顔をして並んでいる写真を撮られていて(笑)。それを試合後に見て大爆笑したことがありました。そんなコーチ陣の中で一人挙げるとすると…ジェフ(勝久ジェフリーAC)は、付き合いも長いので置いておいて、試合中の木下博之ACを挙げたいですね。コーチのアツさは僕の推しポイントです。
北 僕はそれを上から見ていて、コーチがあまりにもみんなアツくなるから「誰か1人でいいから冷静にいるヤツを決めろ」と言ったんですよ(笑)。みんなベンチで立っちゃうので「それを止めるコーチを決めろ」って。そういうコーチ陣が出てくるかが一つの注目ポイントです(笑)。
あと、皆さんの前に出て行くことがないので、推しポイントになるか分かりませんが、プレーヤーディベロップメントコーチの関谷悠介が選手含めたチームの中で一番声を出しています。声がすごく大きいので、彼はどこにいるのかがすぐに分かりますね(笑)。今までの川崎にはいなかったキャラクターです。それに、新加入選手4人もそれぞれの色を出してチームに溶け込んでくれているので、そこはGMとして良かったなと思いますし、うれしいですね。
──川崎ブレイブサンダースというクラブの未来について、今どんなことを考えていますか?
佐藤 1950年にチームが誕生して、長い歴史の中でいろいろな方々の思いがつながってきた結果、今の川崎があります。それをしっかりと引き継いで、川崎というクラブが作ってきた軸に沿ってチームを前進させることが、今の僕の責任だと思っています。それをひたすらやり続けて未来につないでいきたいですし、今やれることにフォーカスしていきたいなと思います。
北 今季はニックのラストシーズンということで、有終の美を飾ってほしいというのが一つ。もう少し先の話をすると、2026年にBプレミアができて、その先に新アリーナの開業が待っています。そのときに川崎という街がどうなっているのかが楽しみです。先は長いですが、ますますクラブとして成長して行くことが大切。チームとしても、やっぱり魅力あるチームでありたいですし、プロスポーツである以上は常勝でありたい。そこも考えながらチームを作っていきたいです。
写真/山岡邦彦、取材・文/堀内涼(月刊バスケットボール)