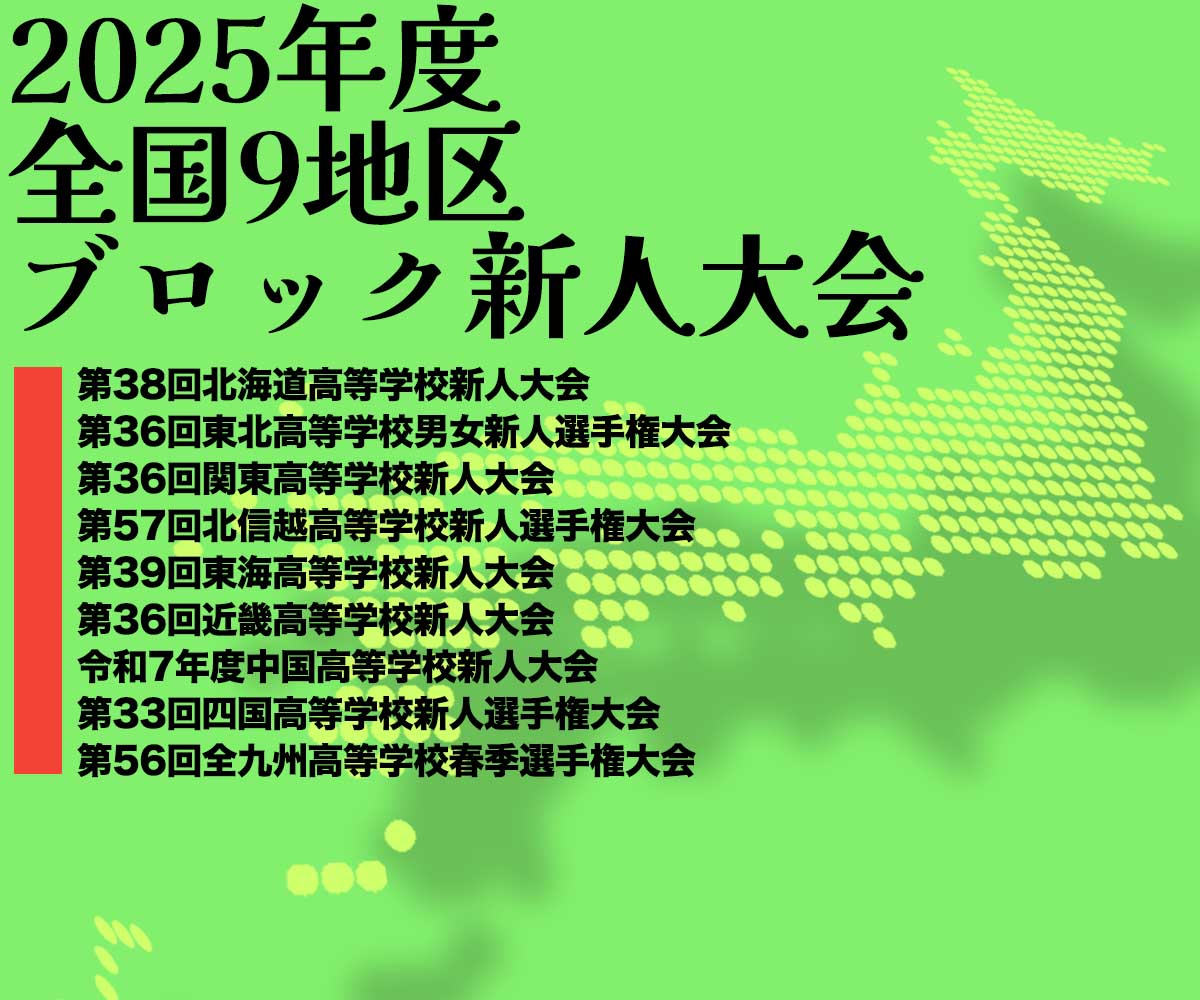ERUTLUC鈴木良和コーチを指導者インタビューで特集!
9月25日発売の月刊バスケットボール11月号では、第45回指導者インタビューに鈴木良和コーチが登場!
東京2020オリンピックでは男子日本代表のサポートスタッフ、FIBA女子アジアカップ2021では女子日本代表のアシスタントコーチを務める鈴木コーチ。大学院生時代に「バスケットボールの家庭教師」という事業をスタートさせ、その後、株式会社ERUTLUC(エルトラック)を立ち上げて活動を続けてきた。一人一人がなりうる最高の自分に近付けるようサポートすることをモットーに、育成年代を中心とした選手たちを指導しながら、同時に指導者たちを育成。今回のインタビューでは、そんな鈴木コーチの学生時代から現在に至るまでの歩みやエルトラックの理念、掲げるミッションについて、情熱あふれるお話をたっぷりと聞いた。
(下記に一部抜粋)

子どもたちから課題を奪わず
自分の頭で考える土台を作る
――鈴木コーチが小学生や中学生を指導する現場を見ていて、選手たちが目を輝かせて聞き入っているのが印象的でした。
ありがとうございます。でも特別に何かをしているわけではなく、とにかく全力でやっているだけです。『伝えたいことがあるんだ!』と情熱を持って接することで、子どもたちも耳を傾けてくれる。もちろん技術やスキル的な議論などで、選手たちに『なるほどな』と興味を持たせることも大事ですが、そもそも『この人の話をちょっと聞いてみようかな』と思わせるにはこちらの全力な熱量がなければいけません。
あとは、僕自身もいろいろな指導者のコーチングに触れ、たくさんの本を読んで、伝え方を常に勉強しています。良い言葉を見付けて自分の中にストックするというか、自分の言いたいことに肉付けしていく。たくさんの言葉と出会う際に、自分のアンテナを張って『あ、この言葉はいいな』とか『この言い方は伝わりやすいな』と集めていくんです。僕自身のコーチングというよりは、いろいろな人たちの良い言葉を勉強して収集して、自分なりにアレンジして使っているだけですね。
結局、コーチングというのは相手にどう伝わるか。たくさんの理論を知っていても、言葉のレベルが低くて相手に少ししか伝わらなければ意味がないですよね。だから理論を学ぶのと同じくらい、伝えるレベルを上げることも大事です。その上、指導者の理論と伝えるレベルが100だとしても、相手の『この人の話を聞きたい!』というレベルが100でないと、100は受け取ってもらえない。だから指導者の力量は、持っている理論や伝える話術などではなく、相手がどれだけ受け取ったかで測るものだと思います。
――相手の「この人の話を聞きたい」「学びを吸収したい」という意欲は、どうやって引き出すものなのでしょうか?
それは本当に千差万別で、コーチングの難しくもあり面白いところです。例えば日本代表選手ともなれば、彼らが直面している課題の克服に対してコーチが持っている引き出しが有効だと感じてもらえれば『もっと話を聞きたい』となるかもしれない。でもバスケットを始めたばかりの子に「日本代表の課題は…」なんて話をしても、ポカンとされて全然意欲は湧かないですよね。それよりも単純に「面白い!」と感じてもらえるような、ゲーム要素を入れた練習をした方が『もっと話を聞きたい』となるかもしれない。相手の興味を引くために唯一正しい答えがあるわけではなく、人や状況によって手段は全然違ってくると思います。相手が何を求め、どんな課題を持っているのかを察知し、相手を引き付ける手段を導き出す力が必要です。

写真は2017年
――以前、「選手に課題を与える」ことの大切さを話されていましたね。
正確に言えば、子どもたちがスポーツをする上で「課題を奪わない」ことが大事だと考えています。バスケットで上達を目指す以上、課題は必ず出てくるもので、例えばリバウンドが全然取れなくて試合に負けたとする。そのとき選手が「もっとリバウンドを取るには?」と考えて、「こういう練習をしたらどうか」「こうやってボックスアウトしたら取れるのではないか」と試行錯誤していけば、その選手は自ら課題を解決しようとしていますよね。この繰り返しによって選手はすごく成長するのですが、そうやって選手が解決策を考える前に指導者が「こうすればいいんだ」「こうしないから負けるんだ」と、課題を奪ってしまうことがあります。指導者が先に課題を解決しようとすると、選手は自分の頭で考えずに与えられた解決法に取り組むだけになってしまう。それはバスケットから離れた後の未来にも悪影響です。僕たちの仕事は課題を解決することではなく、選手たちが解決できるようにサポートすること。そうなると、子どもたちに上手に課題を与えていくことも一つの育成方法です。課題を意識しないまま練習したり、間違った課題を克服しようとしたりするのは成長につながりませんから。
――「課題を奪う」というのは、“教え過ぎ”によって選手の主体性を奪うことにもつながりますね。
そうですね。僕が思う「教え過ぎ」の定義は、選手に考えることを放棄させることです。たとえ、たくさんのことを指導者が教えたとしても、選手が自分で考えることをやめていなければ「教え過ぎ」にはなりません。「選手に考えさせたいから放っておこう」と思われる指導者もいるかもしれませんが、要は与えられた知識をヒントにして選手が自分で考え続けられればOKなので、「考えさせること」と「多くを教えること」は両立できると感じています。指導者が教える引き出しによって、選手が自分だけでは気付けなかった領域に気付いたり、「じゃあこうしてみよう」と新たなアプローチが増えたりするのならば、育成年代でもどんどん教えるべきです。小・中学生のうちに「自分の頭で考えることをやめない」という土台を作っておけば、社会に出たときにも、そして高校、大学やBリーグ、日本代表など高いレベルに進んでも大いに役立つと思います。
――鈴木コーチは育成年代から日本代表まで見ているわけですが、「自分の頭で考えて課題を解決すること」はどのカテゴリーでも必要なのですね。
はい。特にワールドカップやオリンピックに関わって、より強くそう感じました。もともと、考える癖を付けることはバスケットをやめて社会に出たときにこそ価値が発揮されるものだと思っていたんです。でも、実際は世界と戦う上でも絶対に必要なことだなと。というのも、国際大会で実感したのですが、バスケットボールはこちらがやりたいことを相手が壊してくるスポーツ。事前に用意されたものを正しく遂行するだけでなく、自分たちがやりたいことを壊された瞬間にさてどうするかという状況判断の連続で、それはトップレベルにいくほど顕著なんです。だからこそ、相手に主導権を握られるような消極的な姿勢ではなく、自分次第でこのゲームを動かすぞという主体的なオーナーシップがすごく重要だなと。やりたいことを壊されたとき、相手が嫌がるプレーを選択するとか、壊されたものを修正して実行するとか、その瞬間、瞬間にコート上で判断するのは選手自身です。そうなると、育成年代から自分の頭で考えて課題を解決することに慣れておくのは本当に大事なことなのです。育成年代を知る僕が現在、日本代表に関わらせてもらっている意味は、単純に代表チームをサポートすることだけでなく、トップと育成年代をつなぐことにもあると感じています。その一つとして、育成年代から選手自身が考えて課題を解決していくことの重要性は、これからも強調して伝えていきたいです。
(取材・中村麻衣子/月刊バスケットボール)