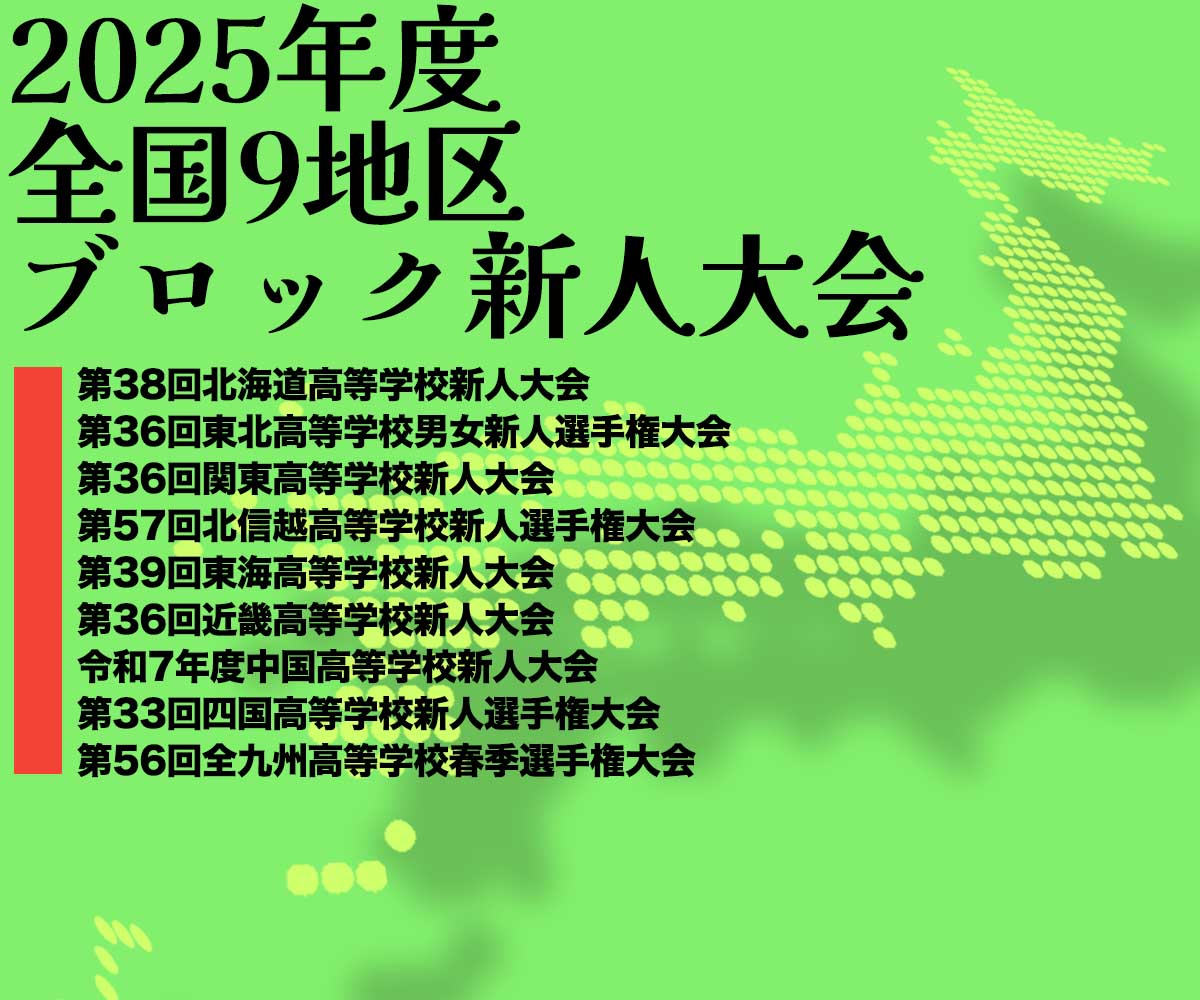河村勇輝&篠山竜青、点取り合戦のオールスターで見せた“ガチ”のダブルチーム
メインイベントとなった2日目のオールスターゲーム本戦は、B.BLACKが127-123でB.WHITEを下し、通算成績を3勝2敗とした。
【写真39点】「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」フォトギャラリーをチェック
この試合では終始3Pシュートの打ち合いが演じられ、B.BLACKが56本、B.WHITEが57本を放ち、前者が19本、後者が20本を成功。試投数、成功数ともに全5回のオールスターゲームの最多数を記録し、現代バスケの進化が象徴されるような展開となった。
個々のパフォーマンスに目を移しても、入場時の篠山竜青の“水戸黄門パフォーマンス”に始まり、富樫勇樹(167cm)と河村勇輝(172cm)の“ユウキ対決”のジャンプボール、レギュラーシーズンではなかなか見られないシェーファーアヴィ幸樹の3Pショー(6本成功の計22得点)、それに対抗するかのようなジョシュア・スミスのノージャンプスリー2本、さらにはセバスチャン・サイズやジャック・クーリー、ペリン・ビュフォードらの豪快なスラムダンクなど、見どころ満載のゲームに。

さまざまな好プレーが集まった3146人の観客を沸かせたわけだが、その中でも序盤で大きく試合を沸かせたプレーがあった。それが、河村と篠山竜青による、富樫への“ガチ”のダブルチームだ。
ことが起こったのは1Q残り7分を切った場面。エンドスローを受けた富樫に対して後ろから篠山が決死の表情でスティールを狙ってサイドライン付近に追い込むと、絶妙なタイミングで河村が加勢。
フロントコートに入ってもハードに足を動かし続け、コフィンコーナーに追い込まれた富樫はたまらずボールを失うと、そのボールは河村から今村佳太へとつながり、最後はサイズへの豪快なアリウープとなってB.WHITEはタイムアウトを取らざるを得ない状況になった。
篠山は言わずもがなのリーグ屈指の対人ディフェンダーで、Bリーグでは華麗なアシストや要所の得点が目立つ河村も福岡第一高時代から最強の堅守速攻を先陣する強力なディフェンダーだった。彼らの息の合ったダブルチームはこれまでのオールスターゲームではなかなか見られなかったディフェンス面での好プレーだ。

もちろんショーの一部ではあったが、このプレーについて河村は「試合前に篠山選手から『ディフェンスができるラインナップだから』という話をしてもらって、可能であればトラップなどもできればいいなと思っていました。それで最初、自分たち2人で追い込んでスティールできて良かったです」と狙っていたものであったことをを明かす。
篠山も胸を張って「あれは完全に僕たちの勝ちです!」と、してやったりの表情を浮かべていた。
篠山が河村にかけた言葉通り、B.BLACKには彼ら2人に加えてベストディフェンダー3度受賞の藤井祐眞、運動量豊富なベンドラメ礼生に熊谷航、平尾充庸といった前からプレッシャーをかけられる選手が多かった。
「オールスターゲームには何度か出場させてもらっていて、シーズン中のタフなスケジュールの中でやっているので安全第一な部分があります。だから、どうしても中だるみや緩い時間帯が出てくるので、ゲームの40分の中でちょっとでも何か変えていきたい、お客さんが楽しんでくれるものをと考えていました」と篠山。
出だしで気迫を見せられたら…そんな思いがあの好ディフェンスを生み出したのだ。
Bリーグに限らず、オールスターゲームはあくまでもお祭りであり、過度な接触によるケガを避けるため、そしてエンタメ性を損なわないために本気でディフェンスをすることははぼない。それがオフェンス側の派手なプレーや高得点ゲームにつながるわけだが、一方で本気でないがゆえにどこか観る側の心がアツくならないという側面もある。
その意味では河村と篠山によるダブルチームからの一連のプレーは、オフェンスに目が行きがちなオールスターゲームに変化を加えるピリッと効いたスパイスのようだった。

スティールを食らった側の富樫は、「ワザとに決まってるじゃないですか(笑)」と冗談混じりの返答し、「うまくコーナーに追い込まれた…というより2人を引き寄せたという感じです。狙い通りだったと思います」と、あくまでもショーの一部だったと強調していた。真意はさておき、会場を盛り上げるという面では富樫の“やられ方”も含めて最高のパフォーマンスだったと言えるだろう。
次回の開催地は沖縄だ。来年もまた、“ガチ”のパフォーマンスを見せてくれることに期待したい。
★「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITOチャリティーオークション」をヤフオク!で開催、B.LEAGUE選手のサイン入りユニフォームを出品。詳しくはこちら。
写真/©︎B.LEAGUE、取材・文/堀内涼(月刊バスケットボール)