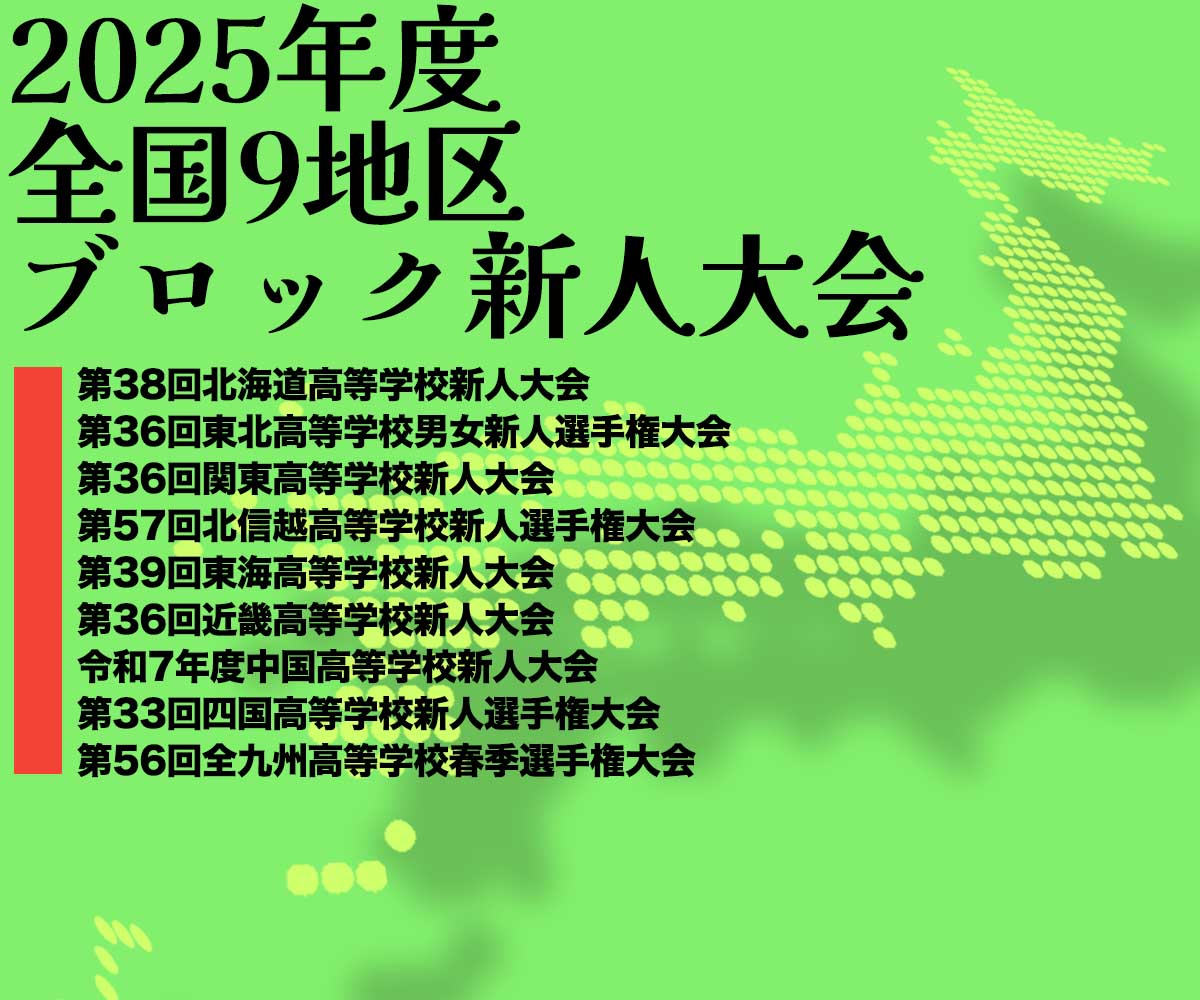安間志織インタビュー - ブンデスリーガに残した小さな巨人の足跡(2)

写真©ShioriYasuma/Eisvögel USC Freiburg
ブンデスリーガのレギュラーシーズンをリーグ2位で終えたアイスフォーゲルUSCフライブルクは、プレーオフの最初のラウンドとなるクォーターファイナルでBCファーマサーブ・マーブルクを2勝1敗で、セミファイナルでルトロニック・スターズ・ケルターンを2勝0敗で下し、ファイナル進出を果たした。
安間はマーブルクとのシリーズで初戦(22得点、11アシスト)と第2戦(11得点、12アシスト)で続けてダブルダブルを記録し、3試合のアベレージでも平均17.3得点、10.0アシストのダブルダブルに乗せていた。続くセミファイナルラウンドでも19.0得点、5.0アシスト。対戦した両チームとすればたまったものではなかっただろう。
ファイナルで対戦したのは、レギュラーシーズンでアイスフォーゲルの上を行くリーグ1位の座を確保したラインラント・ライオンズ。アイスフォーゲルにとっては唯一2度敗れた相手だったが、このシリーズでは初戦こそ落としたものの以降3試合で白星を重ねて王座をつかんでいる。安間はこのシリーズの4試合でも平均16.3得点、6.0リバウンド、5.3アシスト、1.5スティールとハイレベルなパフォーマンスを維持した。
チームを初のリーグ制覇に導き「わぁ!本当に勝っちゃった!」
――ファイナルで倒したラインラント・ライオンズとはレギュラーシーズンの2試合がまったくちがう展開でどちらも黒星(初戦89-96、第2戦55-61)でした。ファイナルでは、試合ごとのスカウティングや一日置きの日程などが影響したことをハラルド・ヤンソンHCは話していましたが、安間さんとしてはどんなねらいを持って戦っていたのですか?
レギュラーシーズンの2つのゲームでは、まったく私たちのチームらしいプレーをできないまま相手のリズムで戦ってあの点差だったので、私たちの走るバスケットができたら勝てるというのをみんなで話していました。その上に、コーチも言っていたとおりチームの健康状態やスケジュール、こちらの若さや相手に年齢が上の人が多いといった要素があり、こっちにはアドバンテージしかないと自信を持っていました。
私たちのチームは70点以上のハイスコアな展開では勝てていることが多く、ファイナルで負けた第1戦もロースコア(59-69)でした。速い展開に持ち込みたかったので、どんなに重くても走り続けるうちに流れが来ると思ってプッシュし続けるということが頭にありました。その中でコーチ陣が言うアジャストをチームのみんなが遂行していたと思います。
特にアウェイでの延長戦に勝った第3戦(78-72)で、第4Qに走って追いついた後、延長が始まるまでのインターバルには、みんなが口をそろえて「ここから私たちのゲームだよ」と話していました。相手は2試合目にこちらのホームで負けた(70-66でアイスフォーゲルが勝利)後だし、今日の3試合目で疲れています。私たちがここから走れれば必ず勝てるとわかっていました。
――その延長戦勝利の翌々日、ホームでの第4戦に勝利(95-65)して、チーム初のチャンピオンシップ獲得となりました。あの後、率直な感想はどんなものでしたか?
勝った直後は、「わぁ!本当に勝っちゃった!」と思いました。シーズンが開幕する前、私が初めて練習に参加した頃はまさか優勝できるとは思っていなかったです。シーズンが進んでいくにつれてチーム全員で優勝への意識が強くなっていきましたが、「本当に勝てちゃった!」というのが正直な気落ちでした。
海外に挑戦してこうして結果を残せたこと、チームの仲間たちと一緒にチームの初優勝に貢献できたこと、またみんなが喜んでいた姿を見ることができて、とてもうれしかったです!
――どうしてうまくいったのだと思いますか?
コーチ陣も含め、チームが組織として私をサポートしてくれました。最初の頃チームでのワークアウトや練習が物足りなくて、やる場所も見つけられないというときにコーチに相談したら別のジムを用意してくれたり、英語の先生や日本人を紹介してくれたり、サポート環境を整えてもらえたんです。英語の先生のご家族にもすごくお世話になりましたし、ほかの日本人の皆さんは、私をきっかけにバスケットボールを見るようになったと言って喜んでくれました。そうした形でいろいろと用意してもらった状況で、私として練習やバスケットボールに対する準備をきちんとしたいという気持ちでした。
ここまでしてもらって私が手を抜くようなことなどできません。私なりの結果を出したい一心でした。英語も十分には話せない中で、コーチ陣も私にたくさん話しかけてコミュニケーションを取ろうとしてくれて、そのおかげで私からもいろいろと相談ができましたし、話しやすい環境を用意してくれました。アイスフォーゲルじゃなかったら、ここまでサポートしてくれなかったと思います。みんな人が良くて、見知らぬ日本人の私にここまでやってくれるのか…と思いながらのシーズンでした。あの組織、あのチーム、あのメンバーでなければ、私はうまくできていなかったと思います。
――開幕前のインタビューでは、ただ日本から来たという以上のインパクトを残したいと話されていました。今、ご自分ではそれが出来すぎなほどできたか、思ったとおりのことをひとまずできたのか、どんな感覚でしょうか?
その間のような感覚です。まず、正直な感覚としてインパクトは残せたかなと思います。ドイツリーグでプレーしたことで、“日本人”の印象をいろんな地域の人たちに見てもらえたんじゃないかな、そうだといいなと思います。
――ドイツではアスリートに男女格差があり、それは是正されるべきということをヤンソンHCが別のインタビューで話されていました。そのような意味合いでも安間さんのご活躍がドイツのスポーツ界に影響をもたらしたのではないかと思いますが、ご自身ではどう思いますか?
あまり自分でその部分に貢献できたとは感じないですけれど、コーチはそういうことを普段から話していました。バスケットボール界の女子があるべき姿(得るべき社会的評価)を話したり、コーチ自身もこれからも戦わなければいけないという話だったり。「(目指すべき状態の)完成が、自分たちが生きている間にできるかはわからないけれどね…」とも言いながら、「昔と比べれば想像できないくらいずっと良くなっていると思うし、今からもっと良くなる」と話してくれていました。もし私たちの優勝でフライブルクに女子バスケットボールを広めることができていたら、なおさら良いと思います。
――迎えた側のドイツに残したインパクトは大きかったと思います。逆に安間さんとして、海外挑戦をやってよかったと思える価値はどんなところにありますか?
バスケットボールをしにいくんですけど、やっぱり海外に行って違う世界を見ることや人とのつながりです。行かなければ今のチームメイトともコーチ陣とも出会えなかったし、本当に私はこのチームの人たちが大好きです。文化の点でも、私にはいろいろな新しいことが面白くて、ドイツの子たちもみんな「やってごらんよ」と言ってくれるので、私も興味を持ててやってみようという気持ちになりました。新しい文化を学ぶとか人との出会いという点で、本当に行ってよかったなと思います。
バスケットボールの面では、日本だと時差もあって、ヨーロッパのほかの国の人たちにあまり見てもらえないと思うんですよね。その点ドイツのリーグでプレーしていると、ヨーロッパに情報が発信されていきますから、広く見てもらうのによいのではないかと思います。ドイツ国内でもいろんな国籍の方がいますしね。日本ではプレーする相手も日本人になりますが、ドイツでは各国のプレーヤーを知ることもできます。

写真©ShioriYasuma/Eisvögel USC Freiburg
「機会があって自分が行きたいと思ったら、やってみた方が良い」
――海外でのプレーは今後もやってみたいお気持ちですか?
そうですね、チャンスがあればやってみたいです。あまり深くは考えていませんが、一年一年やっていけばその先どこかにつながると思っています。チャンスがあって自分でも惹かれるところなら、私は行くと思います。
――日本の子どもたちにも大いに刺激になったに違いありません。何か伝えたいことはありますか?
今、バスケットボールでも海外志向が増えてきていると思います。挑戦は年齢が上がってからでもできるかもしれないし、日本にいる方がプラスのこともマイナスのこともあり、海外に行っても同じようにマイナスもプラスもあるでしょう。でも、やっぱり機会があって自分が行きたいと思ったら、やってみた方が良いと思います。そういう機会は自分から探しにいかないと巡ってきませんし、行動すること自体が難しいとも思うんですよね。
バスケットボールを楽しみながら、だけどこれからはバスケットボールだけじゃないとも思います。私は自分が楽しそうだなと思う方向を大事にしたいと思い、小さくてもできるというのをドイツでやりたい、インパクトを残したいという思いがありました。日本人が一般的にちっちゃいというのはわかりきっていることで、挑戦できる場所もあって、挑戦したいという思いを身近な人に打ち明けるという行動ができました。私を見てくれた人たちに、そういう点で少しでもお手本を示せたとしたらうれしいと思います。

写真©ShioriYasuma/Eisvögel USC Freiburg
取材・文/柴田 健(月バス.com)
(月刊バスケットボール)